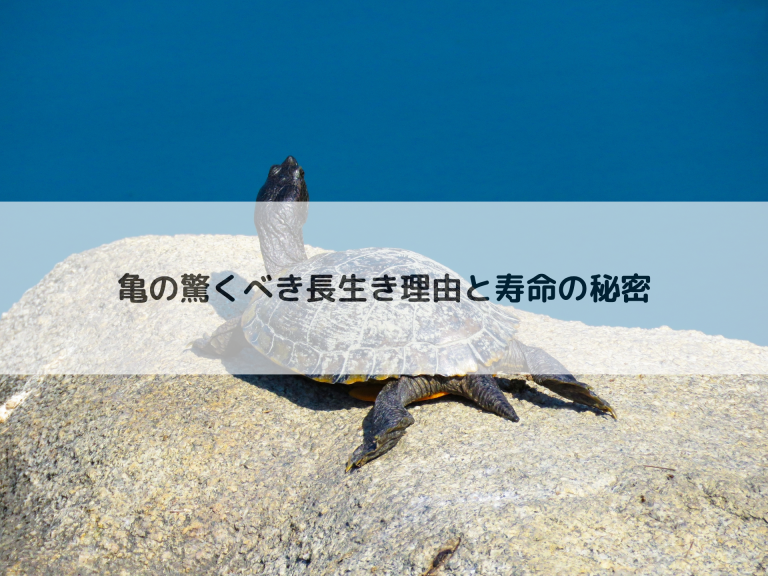カメは、その長い寿命から「鶴は千年、亀は万年」ということわざで知られ、古くから長寿の象徴とされてきました。
ペットとしても人気のあるカメですが、一体なぜこれほど長生きできるのでしょうか。
そこで今回は、カメが長生きする理由に迫り、その驚くべき生態と寿命について解説します。
□亀が長生きする理由
カメが長寿である理由は、いくつかの要因が複合的に作用していると考えられています。
その中でも特に注目されているのが、代謝の低さ、呼吸の抑制、そして甲羅というユニークな体の構造です。
*代謝が低いこと
生き物の寿命は、その代謝のスピードと深く関係しています。
代謝とは、食物からエネルギーを生み出す生命活動のことで、この過程で酸素が消費され、活性酸素が発生します。
活性酸素は、生体にとって必要な役割も担いますが、過剰になると細胞を傷つけ、老化を促進する原因となります。
カメは、心拍数が非常に少ない生き物であり、これは体内に取り込まれる酸素の量が少なく、結果として活性酸素の発生が抑えられることを意味します。
この低い代謝率が、老化の進行を緩やかにし、長寿に大きく寄与していると考えられています。
*呼吸の抑制
カメの呼吸の仕方も、長寿の秘密の一つです。
危険を感じた際に頭や手足を甲羅に引っ込める際、カメは肺の中の空気を最大限に吐き出します。
これにより、甲羅の中に体を完全に収めることができるのです。
この呼吸をほとんどしない状態は、体内の酸素消費量を大幅に削減することにつながります。
この呼吸の抑制は、心拍数を低く保ち、代謝をさらに緩やかにする効果をもたらします。
このように、カメは生命維持に必要なエネルギー消費を最小限に抑える、非常に効率的な省エネシステムを持っていると言えます。
*甲羅の役割
カメの最大の特徴である甲羅は、単なる防御のためだけではなく、その生態や長寿にも深く関わっています。
甲羅は、脊椎骨、肋骨、胸骨などが一体となって形成されており、カメ自身の身体の一部です。
陸棲のカメの甲羅はドーム状で、水棲のカメは水の抵抗を減らすために平らな形をしています。
甲羅の形成にはカルシウムが不可欠であり、その吸収にはビタミンD3が必要です。
ビタミンD3は、カメが日光浴をすることで生成されるため、カメが頻繁に日光浴をする姿が見られるのは、健康維持のために非常に重要な行動なのです。
また、甲羅に身を隠すことで、捕食者から身を守り、安全な環境を確保できることも、長生きに寄与していると言えるでしょう。
□亀の寿命と種類
カメの寿命は、その種類によって大きく異なります。
一般的に、大型のリクガメは非常に長生きすることで知られていますが、小型の種類や水棲のカメは、それよりも短い寿命を持つ傾向があります。
*種類による寿命の違い
ペットとしてよく飼育される小型のカメ、例えばクサガメやニホンイシガメの寿命は、野生下では平均20年ほどですが、飼育環境によってはそれ以上生きることもあります。
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)も同様に、野生下では平均15年ほどと言われています。
一方、ロシアリクガメ、ヘルマンリクガメ、ギリシャリクガメといった比較的小型の陸生ガメは、30年から50年ほどの寿命を持つとされています。
ウミガメについては正確な寿命は把握されていませんが、アカウミガメなどは70年から80年ほど生きると推測されています。
*長寿な亀の具体例
カメの長寿ぶりを示す例として、ゾウガメの存在は特筆すべきです。
イギリス領セントヘレナ島に生息するアルダブラゾウガメのジョナサンは、推定184歳という驚異的な年齢で、現在存命中の動物としては世界最高齢とされています。
また、過去には188歳以上生きたとされるホウシャガメのトゥイ・マリラや、250年以上生きた可能性のあるアドワイチャといったゾウガメの記録も存在します。
これらの大型リクガメは、平均寿命が150年ほどとも言われており、カメの長寿の代表格と言えるでしょう。
□まとめ
カメが長生きする理由は、心拍数が少なく代謝が遅いこと、そして甲羅に身を隠す際に呼吸を抑制する生態にあります。
これらの要因が組み合わさることで、老化の進行を遅らせ、驚異的な長寿を実現しています。
カメの寿命は種類によって大きく異なりますが、大型のリクガメなどは数百年を生きることも珍しくありません。
カメのゆったりとしたスローライフは、私たち人間にも、穏やかな時間の過ごし方を教えてくれるかのようです。